ずっと、行きたかった国がある。
それは、アイスランド。
まだ一度も訪れたことがないのに、
なぜか——「自分はあの地に属している」と感じていた。
そう思うようになったのは、好きになったアーティストたちが
不思議と皆、アイスランドにルーツを持っていたからかもしれない。
Björk、SIGUR RÓS、Ólafur Arnalds、Kiasmos…
惹かれる音をたどってゆくと、必ずその源流にアイスランドがある。
だから、彼らのインスピレーションの根にある
あの広大な自然の中で、彼らの音楽を聴いてみたかった。
耳を澄まし、心をひらいて、その風景と旋律に身を委ねてみたかったのだ。
音楽を、もっと深く感じたかった。
この美しい国と、自分自身がつながっていくのを確かめたかった。
そして──
その体験には、季節が欠かせなかった。
僕にとって彼らの音楽は、夏ではなく、冬だった。
吹き荒れる風、ひび割れる氷河の音、
雲間からわずかに射し込む陽のぬくもり…
そのすべてが、厳しくも美しい冬の賛歌のようだった。
ようやく、今年の冬。
僕はその地を訪れることができた。
想像を遥かに超える美しさが、そこにあった。
はじめて訪れたはずの場所なのに、不思議な懐かしさに包まれる。
この国とは、やはり深い親和性があるのだと感じた。
ある日、西の都レイキャビクから、東の氷河へと旅に出た。
一日では辿り着けないので、途中の南の街で1泊することにした。
凍てつく大地の途中でやさしいぬくもりがあるホテルだった。
翌朝、ホテルを後にして闇の中、低く光る月を横目に見ながら、車を走らせる。
夜明け前の静けさに包まれたまま、目的地に辿り着く。
そしてそのとき、ちょうど陽が昇り始めた。
氷河を、朝焼けがゆっくりと染めていく。
その光景は、きっと一生、心から消えない。
「今だ」と思った。
イヤホンを耳にあてる。
迷わず選んだ曲は、Björkの “Hyper-Ballad”。
ボリュームを最大まで上げる。
浮遊するようなリズムが、水平線から太陽を持ち上げていく。
後半に向けて伸びやかに解放されていく彼女の声が、
張り詰めた冬の空気をやわらかく溶かしてゆく。
──この曲は、倦怠期を迎えた恋人たちの歌らしい。
けれど今の僕には、目の前の風景と完璧に重なって聞こえる。
歌詞に出てくる「崖」も、きっとこの崖だと思えてしまう。
イヤホンのはずなのに、まるで彼女が目の前で歌っているようだ。
音が、僕の耳に、心に、全身に、降り注ぐ。
その振動が、僕とこの氷の大地を、静かに、確かにつなぎとめていた。
このエッセイに登場するホテル

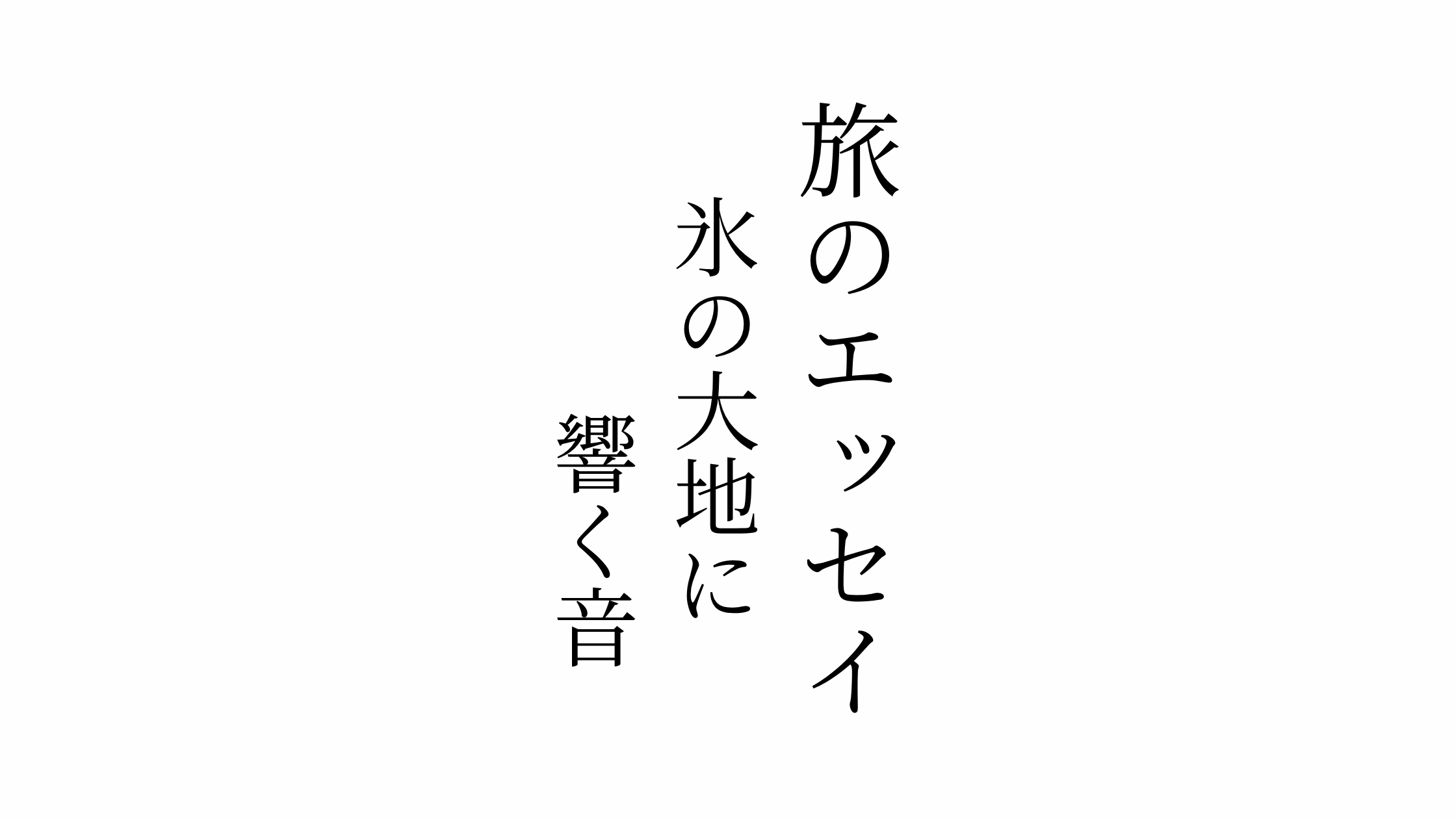



コメント