異国をひとりで旅していると、不思議なほど、よく声をかけられる。
決まり文句のひとつは、「ここを案内しようか?」というものだ。
たいていは、あまりにありがちな罠。
親切の仮面の奥に、金銭を狙う素顔が見え隠れする。
けれど時に、直感が語りかけてくる。
「この人は、きっと大丈夫だ」と。
そんなとき、好奇心が勝ってしまうのだ。
ハノイの旧市街で声をかけてきた彼も、そんなひとりだった。
名はジェームス。
「もし、必要なら——バイクで街を案内してもいいよ」
彼は、確かに if you need と言った。
それが、押しつけがましくなくて、心地よかった。
落ち着いた声に、誠実さが宿っていた。
気付いたら、「じゃあ、お願い」と答えていた。
*
翌日、ホテルのロビー。
約束の時間にほんとうに、ジェームスはやって来た。
ハノイの中心から少し離れたホテルだったし、半分、来ないだろうと思っていた。
だから現れたとき、「疑ってすまない」と声に出さずに謝った。
彼は、僕の分のヘルメットとマスクまで用意してくれていた。
ハノイのバイク乗りは、砂埃のため、マスクが欠かせない。
その気遣いに、静かな優しさを感じた。
「準備はいい? 行こう」
バイクにまたがり、彼の背中にしがみつく。
合図のように、エンジンが風を切る音を立てた。
これがハノイ名物。
まるで生きもののようにうねるバイクの群れ。
ジェームスはそのうねりの中を、迷いなく駆け抜けていく。
あまりにスリリングで、最初は少し怖かった。
けれど次第に、それも愉しみに変わっていった。
観光名所ではバイクを停め、ベストスポットで写真を撮ってくれる。
そのたびにヘルメットを外すのだが、慣れない僕はいつももたつく。
「君はまるで赤ちゃんだね」
呆れ顔のジェームスが、優しく手を貸してくれる。
そうやって、少しずつ、距離が近づいていく。
文廟、オペラハウス、ハノイ大教会、ホアンキエム湖…
僕らはハノイの風になった。
照りつける陽射しが、ふたりの心を照らし、
街を駆け抜ける風が、笑い声を運んでいく。
鳴りやまぬクラクションでさえ、ふたりだけの音楽に聴こえた。
その瞬間、世界のなかで、僕らだけが特別に輝いているようだった。
昼過ぎ、彼のおすすめのシーフード店で蟹を山ほど平らげた。
もう食べられない、と笑いながらも、皿の上は空っぽだった。
駐車場へ向かう帰り道、ふいに肩を組まれて言われた。
「なあ、おれたち、こうしてると兄弟みたいじゃないか?」
赤ちゃんから、兄弟へ。
僕はひとつ、大人になったらしい。
ジェームスツアーの終わりも、彼はちゃんとホテルまで送り届けてくれた。
最後の最後まで、彼は紳士だった。
*
日本に戻ってからも、時々、彼からメッセージが届く。
「無事に着いたか?兄弟」
「転職おめでとう、兄弟。うまくいくといいな!」
ハノイの風景に溶け込むように、忘れがたい思い出となったジェームスとの一日。
See you soon, bro.
このエッセイに登場するホテル

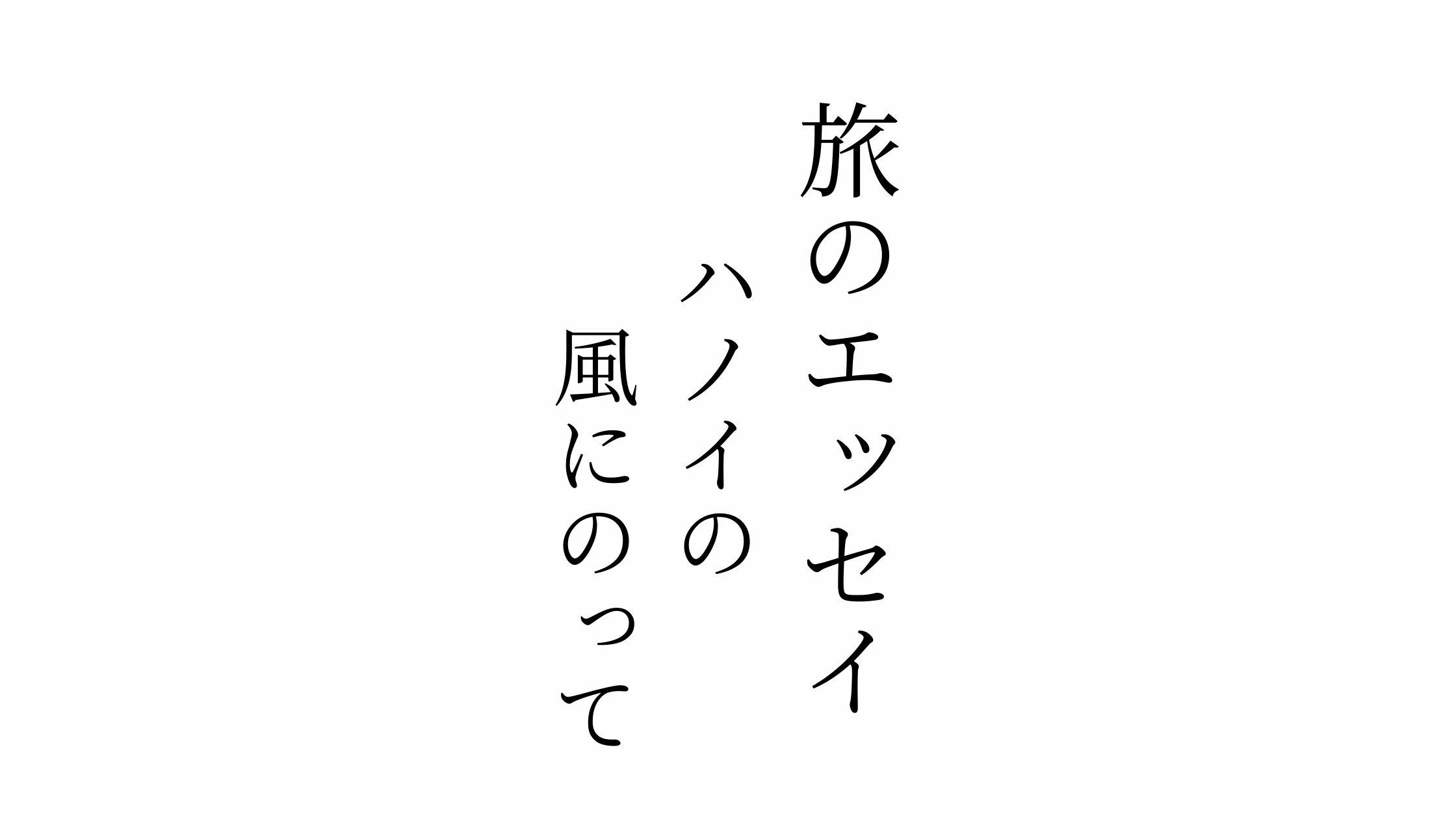



コメント